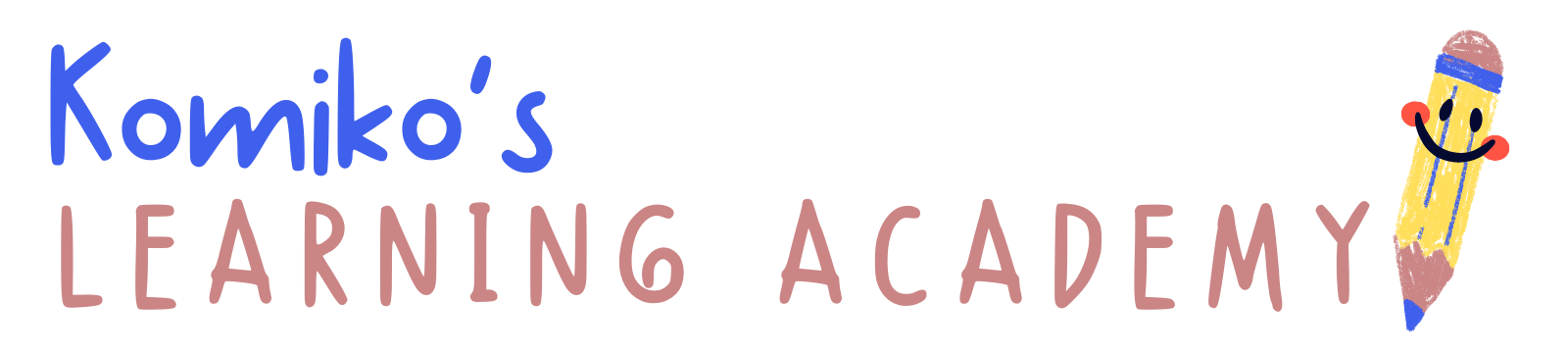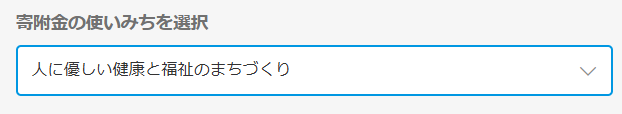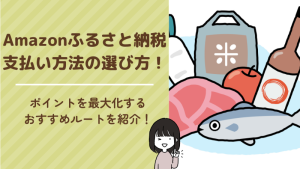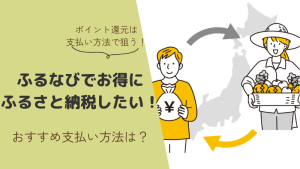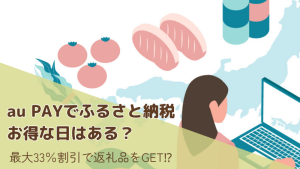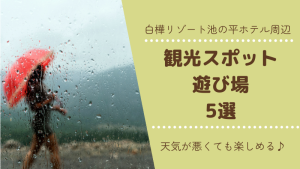うちの子、社会の勉強が苦手みたい…



小学生が楽しく社会の勉強をする方法はないかな?
こんなお悩みを抱えていませんか?



小中学校英語科教員歴13年のKOMIKOです!
現役教員である私が今の小学生を見ていると、社会の勉強は好きと嫌いが大きく分かれる教科のようです。
本記事では、ふるさと納税を小学生の社会の勉強に活用してほしい理由とその活用法について解説します。
- ふるさと納税を通して学習できることは「税の仕組み」、「地域の産業」、「日本の地理」の3つ
- 手元に特産品が来る実体験の組み合わせで記憶の定着力がUP
1つずつさらに詳しく解説していきます!
ふるさと納税を社会科の学習におすすめする理由3選
ふるさと納税は、「寄付をすることでお礼の特産品をもらえ、寄付金の一部は税金の控除を受けられる仕組み」です。
小学生にとっては少し難しく感じるかもしれませんが、実はこのふるさと納税、社会科の学習と深くつながっています!
ふるさと納税を通して社会の学習を深めることができる理由は以下の3つです。
- 税の仕組みを学べる
- 各地域の産業を学べる
- 日本の地理を学べる
どれも小学生の社会科の学習で必ず出てくる項目ですよね。
それぞれ詳しく解説していきます。
ふるさと納税を社会科の学習におすすめする理由①:税の仕組みを学べる


ふるさと納税は、寄付をすると税金が控除される仕組みになっており、普段の生活ではあまり意識することのない税金について学ぶ良いきっかけになります。
小学生にとって税金は難しいテーマですよね。
しかし、保護者と一緒にふるさと納税を体験することで、「お金を払うとどう役立つのか」「なぜみんなで税金を集める必要があるのか」といった社会の仕組みを具体的に理解できるようになります。
また、ふるさと納税では、寄付したお金の使い道を選択することが可能です。
例えば「教育」、「文化遺産の保護」、「環境保護」など、どの地域・どの分野の取り組みにお金を使うのかを決定する過程で「自分のお金が社会の役に立っている」というリアルな学びを得られます。
ふるさと納税は「税金」という難しい学習テーマを実生活に結びつける教材として活用することができます!
ふるさと納税を社会科の学習におすすめする理由②:各地域の産業を学べる


ふるさと納税を社会科の学習におすすめする理由の2つ目は、「各地域の産業を生活の中で実感しながら学べる」点です。
学校の社会科の授業では農業や漁業など、日本の産業について学習をします。
しかし教科書や資料の勉強は抽象的で具体的なイメージをつかみにくく、その結果知識の定着が難しくなります。
ふるさと納税を通じて実際の地域の特産品を目にする・選ぶ・味わうという実体験が加わることで、知識が具体的になり、理解がぐっと深まります。
- 鹿児島県の黒豚を返礼品に選ぶことで、畜産業の特色や飼育方法に関心が広がる
- 山形県のさくらんぼを選ぶことで、気候条件や果樹農家の工夫に目を向けるきっかけになる
「青森のりんごおいしかったな~」「愛媛のみかんはどうだろう?」
食べることは子どもにとって最大の楽しみ♪
楽しみながら地域の特産品について学びを深めることができますよ。



ふるさと納税は単なる寄付制度ではなく、社会科の学びを体験的に広げるための教材として活用できます!
ふるさと納税を社会科の学習におすすめする理由③:日本の地理・歴史を学べる
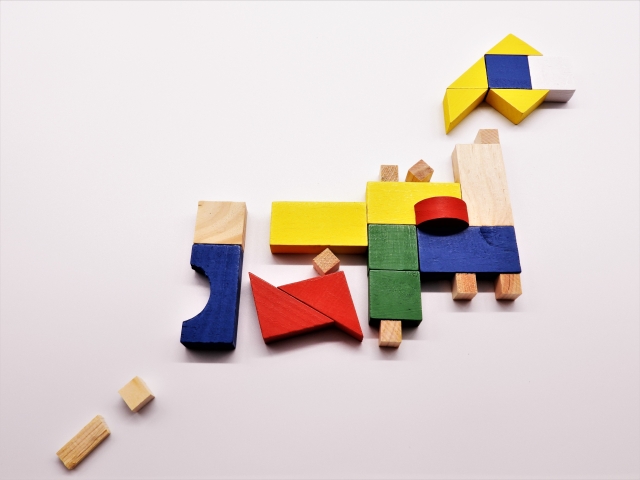
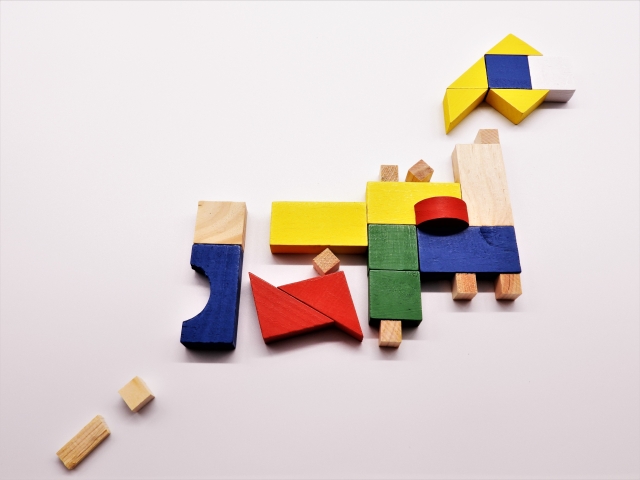
ふるさと納税は、日本の地理・歴史を学習するうえでも非常に役立つ制度です。
全国のさまざまな自治体にふるさと納税を行う過程で、子どもは「どの地域がどの特産品で有名なのか」を学びます。
ここまできたら、もう1歩さらに学習を深めましょう!
青森でりんごが生産されているのはなぜだろう?
これが、ふるさと納税を社会科の学習におすすめする理由3つ目「日本の地理・歴史を学べる」という点にあたります。
- どのような気候や風土のもとで生産されているのか
- 生産にあたってどのような歴史があるのか
例えば北海道の乳製品や海産物、青森県のりんご、鹿児島県のさつまいもなど、返礼品を通して地域ごとの特色を具体的・包括的に学ぶことができます。
子どもが「なぜこの地域でこの産業が発展しているのか」と疑問を持ち、自分で調べて理解する過程は、知識の定着だけでなく考える力の育成にもつながります。
親子で楽しみながら地域の特色に触れられる点も魅力です♪
実録:親子でできる!ふるさと納税を使った学習の進め方
では実際に親子でふるさと納税を使い社会の学習を進める方法について解説します。
まずは楽天ふるさと納税のページからふるさと納税返礼品をチェック!


おすすめは、
ジャンルから探す>食品・ドリンク>精肉・魚介類・米・フルーツ・野菜・麺類
赤枠で囲ったジャンルです。



愛媛県のみかんおいしいね!じゃあ…
- そもそも愛媛県ってどこにある?(地図の確認)
- 愛媛県のみかんの生産量は?日本で何位かな?
- みかんの種類たくさんありそうだね
- なぜ愛媛でみかんがとれるんだろう?みかんはどういう気候だと良く育つ?
- 日本では何時代からみかんを食べ始めたのかな?
土日など、時間が取れる時に上記の質問を子に投げかけてみてください。
PCやタブレットで調べてしまって構いません。
長時間机に座り、色鉛筆を使ってまとめ学習をする…というのもいいですが、会話をしながら、さらっとでいいんです。
子どもからさらに質問が出ればなおよいですね♪
実体験と結びついた学びが一番記憶に残るので、実際に食べながらのタイミングが◎
こうした体験は、単なる調べ学習にとどまらず「生活と学びがつながる喜び」を実感できる貴重な時間になります。
まとめ:ふるさと納税を社会科の調べ学習に活用しよう!
本記事では、社会の勉強が嫌いな子にふるさと納税を活用してほしい理由とその活用法について解説しました。
- ふるさと納税を通して学習できることは「税の仕組み」、「地域の産業」、「日本の地理」の3つ
- 手元に特産品が来る喜びで、学習へのモチベーションがUP
社会の学習は、今を生きる自分自身につながる学び。
「つながっていること」を実感できると、学びの楽しさが格段にUPします!



ぜひ美味しい楽しいふるさと納税を、社会の学習に役立ててみてくださいね♪